第九回 産業振興とエネルギーの地産地消で徳島を変える!
人口減少と経済低迷からの脱却を目指す者たち
徳島県が「蘇生」に向けて歩み始めている。その契機となったのは新たな知事の誕生だった。トップが変われば県政は大きく変わるといわれる。しかし、いかにトップにやる気があっても、それに応える人びとの思いがクロスオーヴァーしなければ、容易に変化は生まれない。徳島には衰退する地域を何とかしたいという強いミッション(使命感)を抱いた者たちがいる。知事が替わったことで、彼らのとにかく現状を打開せんとするエネルギーが解き放たれ、それが周囲に浸透していき、行政と地域で生きる人びととの共鳴が始まっている。必ず徳島は変わっていく。そう確信する取材となった。
“徳島ショック” と評された最低賃金の大幅引き上げで

徳島県の人口減少率は2024年に国内7位となった。この年、47都道府県のうち、最低の出生率だった東京都の人口だけが増えるなか、東北と四国の人口減少は深刻さを増し、秋田県、青森県、岩手県、山形県、高知県、福島県に次いで徳島県の順で過疎化が進んだ。10年前の2015年6月における徳島県の人口は758,841人、それが2025年の6月時点で678,023人と、この10年間で1割以上も減ってしまった。
そうしたなか、2年前の2023年4月の徳島県知事選で後藤田正純氏が新知事に選出され、その変化の象徴ともいえる出来事が起きた。“徳島ショック”と評された最低賃金の大幅引き上げだ。それまでは「隣の兵庫県との月給が5万円も違うことから、徳島市に住みながら約40分かけて淡路島の病院に通勤している看護師もいた。低賃金が人口の県外流出につながる危険性を示唆する事例だ」と後藤田知事は強調する。
2024年8月、徳島県は最低賃金の算定基準の見直しに着手し、中央最低賃金審議会の50円を大幅に上回る84円まで引き上げ、時給を980円とした。これにより徳島県の最低賃金は国内ワースト2位という状況を脱した。地元中小企業からはコスト高になると一部反発もあったが、激変緩和措置として、時給を980円以上に引き上げた中・小規模事業者に対しては、正規雇用の労働者1人当たり5万円、非正規雇用の労働者は1人当たり3万円の一時金を支給するといったサポートも実施した。そのために準備した11億円の予算からの支出は3億円に抑えられ、なおかつ倒産件数も増えなかった。以降、全国統計では実質賃金がマイナスとなる中、徳島県の実質賃金だけがプラスで推移している。政府とマスメディアの多くが連合傘下の大企業組合の大幅賃上げを喧伝するが、中小企業や非正規労働者の賃上げが低く抑えられれば、いつまでたっても賃金格差が開くばかりで、実質賃金は上がらない。いまは賃金の底上げが必要であることを“徳島ショック”が証明したことになる。
バッテリーバレイ構想とインバウンド招致の3 本柱を力点に

つぎつぎと新施策を打ち出してきたことで知られる後藤田知事から、その根底にある思いを直接聞いてみたいと私は考え続けてきた。そして2025年6月5日、後藤田知事に取材する機会にようやく恵まれた。知事は0~2歳児の保育料無償化を実現すると同時に、徳島県総合看護学校と県立鳴門病院付属看護専門学校、専門学校徳島穴吹カレッジ、徳島医療福祉専門学校、四国歯科衛生士学院専門学校などの私立専門学校の授業料も無償化した。また、NPOが運営主体となる徳島県の子ども食堂は1万箇所を超え、増加率は日本一となった。
「知事のタイプにはガバナンス型と経営者型があるが、自分は後者。前例を踏襲して現状維持をするだけでは人口減少は止まらない、何もしなければ怠慢のそしりを免れ得ない」と後藤田知事。「とにかく内向きになってはいけない」と力を込めて、次の3点を人口減少対策の柱にあげた。
(1)県内企業の輸出を増やす。
(2)一人あたり生産性を伸ばす。
(3)インバウンド(外国からの訪日客)を増やす。
これら3本柱の具体化を目指す中、後藤田知事は2024年7月に「バッテリーバレイ構想」を策定した。徳島県では大きな蓄電池材料メーカーや蓄電池メーカーの立地が進み、蓄電池製造業の製造品出荷額は全国4位(2022年)となっている。この構想では、製造品出荷額を1,603億円(2022年)から3,000億円(2030年)に、従業員数を4,232人(2022年)から5,000人(2030年)に引上げることを目標にしている。
蓄電池産業はハイブリッド車やEV(電気自動車)だけでなく、再生可能エネルギーの供給を安定させるには不可欠な装置を生産し、脱炭素化にとって不可欠な未来産業である。「バッテリーバレイ構想」は、原材料調達から製品生産、リサイクルまでのサプライチェーン企業の誘致、徳島大学と阿南高専だけでなく高校生まで含めた県内全域での人材育成の促進、蓄電池のリサイクル産業への事業拡大、そして製造工程の消費エネルギーの導入を掲げている。輸出を促進するには、RE100(再生可能エネルギー100パーセント)を目指した実践を重ね、環境に優しい企業イメージの確保が必要になってくるだろう。まだまだ課題は多いが、その解決に向けた歩みを徳島県政は着実に進めつつある。

さらにLCC(格安航空会社)を誘致し、徳島空港から韓国・香港の路線を就航させたのはインバウンド招致策の一環だ。2025年1月末には、韓国チェジュ(済州島)との友好協定を結び、少年少女合唱団を含めて国際交流を盛んにしている。インバウンド招致が促進されるだけでなく、徳島から格安航空券で海外体験が可能となった。修学旅行などでも積極的に活用し、英語をはじめとする外国語圏での滞在体験を人材育成につなげる刺激となることを期した取り組みといっていい。
前例踏襲に陥りがちな状況が変わり、新電力が始動
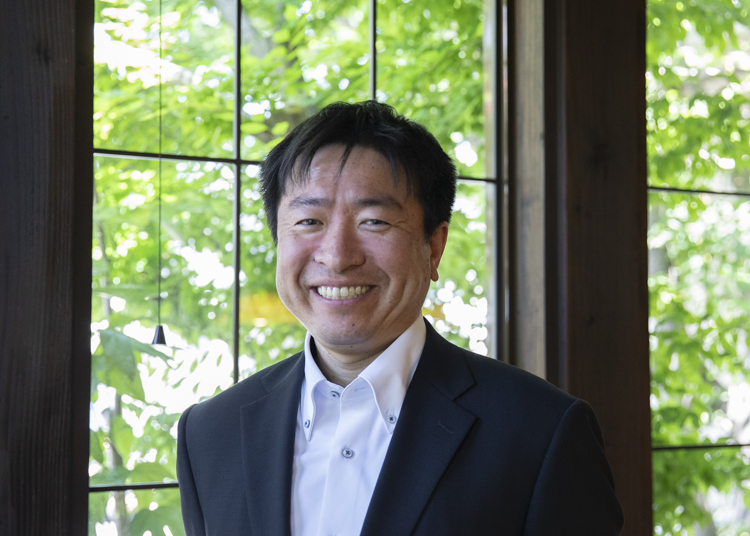
過疎が進む町でも新たな動きが起きている。徳島県那賀町には県が保有する水力発電所がいくつかある。長安口ダムの日野谷発電所(最大出力62000キロワット、常時出力14400キロワット)が最大規模で、川口ダムの川口発電所(最大出力11700キロワット、常時出力3000キロワット)が中規模、一番小規模なのが追立ダムの坂州発電所(最大出力2500キロワット、常時出力120キロワット)だ。その那賀町に2023年11月16日、小さな発電会社が設立された。「那賀川の水を使って発電した電気を那賀町に住む私たちも選んで買えないのはおかしい。那賀町で生まれた電力会社なら、発電事業者の徳島県からふるさとでつくった電気を買うことができるかもしれない。それができれば、町役場をはじめ町が払っている電気代が地域外に流出していくのを地元の収入として取り返すことができるのではないか」と考えた山崎篤史さんら町会議員が中心となり、新電力会社の設立を模索し始めたのが小売電気事業会社設立の原点となった。
吉野川市と小松島市を拠点とする日本中央テレビ(株)社長の山崎さんは、生まれ故郷に戻って町会議員も務めていた。那賀町の出身で中学校まで地元で過ごしたこともあり、ふるさとが急激な人口減少に直面しているのを放っておけないと戻ってきた。1955年に約2万5千人だった町人口は2020年で7367人に。この10年間を見ても、2013年に1万人近くいた人口が2024年には7278人まで減っている。
ふるさとの窮状を何とかしたいと、山崎さんら町会議員たちは、2022年7月頃から他の地域を視察して回り、ゼロカーボンタウン宣言を出した大阪府の能勢豊野町、鳥取県米子のローカルエネジー株式会社を訪ねた。しかし前知事時代には、県も前例踏襲に陥りがちで、新しい電力会社を立ち上げ、県有ダムから電力を購入するという山崎さんたちのプランは実現可能性が低いとの姿勢を崩さなかった。ところが、知事が後藤田知事に替わった2023年4月に状況は変わった。まもなく県営発電所からの15年の売電基本契約が切れようとしており、入札導入の兆しが見えてきたため、山崎さんらは、地域の電力会社が参入できるよう企業局に要望するとともに、地元の受け皿となる新電力の設立を急いだ。

新電力会社の社長となった山崎篤史さんは、前述したように地元ケーブルテレビの日本中央テレビ社長でもある。いくつかの地域のケーブルテレビ会社は、テレビとインターネットと新電力を組み合わせて世帯に供給するビジネスモデルを持っており、視察に行った米子のローカルエナジー(株)もケーブルテレビ会社の関連会社だった。日本中央テレビとともに栃木のケーブルテレビ会社の関連会社・ホームタウンエネジー(株)もそれぞれ35パーセントと5パーセントの出資者となった。山崎さんと町長選で争った那賀町の橋本浩志町長も2023年9月に町が出資者となる形で新電力会社設立への参加を決め、2023年10月に新電力への35パーセント出資のための予算が議会で承認された。そして11月16日には新電力「なかよし電力株式会社」が設立され、同社は2025年1月には追立ダムを備えた坂州発電所との売電契約が成立する。売電電力量は560万キロワットアワーで、末端売電売上額は約2億円を予定している。
那賀町の行政が使用する電力料金は約1億5千万円で、その3分の2の1億円をなかよし電力に切り替える。さらに当面は、那賀町内約3500世帯のうち600世帯をなかよし電力の利用者に切り替えたいとしている。だが、県との既存の売電契約では、四国電力は1キロワットアワー当たり10円程度であったが、なかよし電力は同12円に設定した。新規契約者の獲得が始まったばかりで、当面の人件費を確保するのも難しく、いまは山崎さんが持ち出しで対応せざるを得ず、電気小売部門の専門会社に外部委託を余儀なくされている。補助金や地域おこし協力隊の活用も考えているという。
販売額が5億円に達しないと、自前で専門スタッフをそろえることができない。販売量が増加すると坂州発電所の供給量では不足となる。当面、昼間は再生可能エネルギーを外部の発電設備企業(オフサイトPPA)から仕入れるしかない。いずれ川口発電所の電気を入札で調達できるようにしたいというが、まだまだ先の話になりそうだ。それでも「何とか頑張って切り拓いていきたい」と山崎さんは力を込めて言う。
エネルギー転換の動きを持続させる、自ら「経済」を回す力

過疎地にできた新電力「なかよし電力」を支えてきたのは、一般社団法人・徳島地域エネルギー社長の豊岡和美さんだ。なかよし電力に設立資金として25パーセントを出資するとともに、太陽光発電はもとより、小水力発電、バイオマスボイラーと再生可能エネルギーに関する総合事業の基本設計を担ってきた。「徳島地域エネルギーには、元四国電力管内の発電所副所長の大下浩治さんが在籍し、細かな書類を完璧に用意するための有益で貴重な助言をしてくれたのがとても大きい」と豊岡さん。地方でこれだけ幅広く再生可能エネルギーを取り扱っている事業体は少ない。なぜ、この特異な事業体が徳島で誕生したのだろうか。
豊岡和美さんには、10年前に拙著『負けない人たち』(自由国民社、2016年)の取材でインタビューをしたことがある。子育てをしている2000年1月、吉野川可動堰反対の住民投票を実現させる市民運動にかかわった。2003年4月、県議会議員選挙に市民運動から立候補して当選したが、なかなか政策や法案が通らないこともあり、自民党会派に入った。2期目は落選したが、吉野川可動堰は事実上、塩漬けとなった。
その後、2011年3月に起きた福島第一原発事故を契機にエネルギーの勉強を始めた。勉強会には、企業家や銀行も巻き込んだ。市民が電力会社を作ったドイツのシェーナウにも視察に行った。市民運動を経験して痛感したのは、いくら立派な理念を掲げても訴えが伝わる割合はごくわずかであり、多くの人たちが生活に追われているという現実だった。豊岡さんは「エネルギー転換の動きを持続させるには、自らが『経済』を回していく力を持つことではないか」と言う。

最初は自治体と組んで、3億円規模の1メガワットの太陽光発電所から始めた。4パーセントの金利をつけた私募債(50万円×49口)に加え、資金の8割を阿波銀行からの金利2パーセントの借入金でまかなった。2015年末までにFIT(固定価格買取制度)を使った太陽光発電事業を28カ所、出力15メガワットの発電所建設をコーディネートした。それを基礎に金融機関からの借入の他に、建設費の1割を寄付金でまかない、売電益に応じて地域の特産物を購入して、発電量に応じて購入者に届けるコミュニティハッピーソーラー事業を作り出した。
佐那河内(さなごうち)みつばちソーラー、ゆずの里発電所、海のソーラー牟岐をはじめ事業は10カ所を超え、出力は1.75メガワットに達した。鳴門商工会のコミュニティハッピーソーラー鳴門は、学校の屋上4カ所で合計出力143キロワットの太陽光発電に取り組む。そこでは寄付金300口(300万円)に対して鳴門わかめなどの特産物を返礼するとともに、収益の半分を鳴門市に寄付した。併せて2020年には1.5メガワットの自社ソーラー、佐那河内で小水力発電(50キロワット)を建設している。
広葉樹林を維持しつつ、バイオマスボイラー事業

現在、徳島地域エネルギーのもう一つの大きな柱となっているのがバイオマスボイラー事業である。徳島県職員時代からバイオマス事業がやりたくて、徳島地域エネルギー設立当初からのメンバーになったのが羽里信一さんだ。島根大学農学部で林学を専門とする小池浩一郎教授と同窓なこともあって、小池さんから日本に合うバイオマスボイラーとしてオーストリアのETA社製を勧められていたという。バイオマス発電は燃料の安定的確保やコスト面の課題からなかなか取組みが広がらないが、熱利用の点ではかなり有望なことがわかってきた。しかも化石燃料を使わずに済み、CO2削減効果が大きい。考えてみれば、かつては化石燃料を使わず、薪を使っていた時代もある。
徳島地域エネルギーは2013年に試験的にETA社のボイラーを導入し、毎年社員をETAの研修見学に派遣している。2015年頃から温泉施設やゴルフ場など毎年2~3カ所でボイラーを販売できるようになり、ETAの正規パートナー3社のうちの1社となった。そうしたなか、兵庫県が県有林中心に「北摂里山地域循環共生圏」構想を作成する。880ヘクタールの県有森はもともと新都市構想のために買い取られたものだったが、阪神淡路大震災の発生に伴い計画は頓挫していた。そこで里山地域循環共生圏として活用する方向での転換が進められることになった。


徳島地域エネルギーは、兵庫県に対して県有林の管理をやらせてくれと要請した。そのために、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「エネルギーの森事業」に応募し、資金を獲得した。兵庫県の県有林は広葉樹が中心で、それを伐採し、切断し、チッピング(乾燥チップにする)してバイオマスボイラーの燃料にできる。乾燥チップを作る専門業者の極東開発の協力を得ることができた。NEDOの補助金で事業資金の3分の2が調達でき、フェラバンチャー(伐倒機械)、乾燥コンテナ、ボイラー2台なども購入できた。これによってバイオマスボイラーの燃料確保という課題を解消できるようにもなった。広葉樹を伐採した後は、天然更新を見ながら、間引きしたり、足りない所は植樹したりして森を維持していくことができる。
それだけではない。宝塚造園組合の協力を得て、従来、廃棄処分していた公園の伐採樹木やせん定枝を譲り受けては薪にして5キロ500円で販売するようにもなった。こうした方式を東京に導入すれば、銭湯などの燃料が極めて安価に入手でき、伐採樹木の処理コストはなくなる。身近の生活空間の足元を見直せば、またまだ地球環境の保全に非常に役立つものが眠っているといえそうだ。
民間主導の公益事業体 ドイツのシュタットベルケに引けを取らない事業
徳島地域エネルギーは極めて特異な事業体といえるだろう。市民運動と同じような社会を良くするという強いミッションを持ちながら決して市民運動の域にだけとどまることはなく、事業を持続可能とするための利益を上げなければならないとの強い信念を持つ。営利事業体にして、営利追求だけを自己目的としているわけではない。強いコンサルティング力を持ちながら、単なるコンサルティング会社ではない。今時の言い方を真似れば、公共精神を強く持ったマルチソリューション事業体といったところか。
地域にニーズや意欲を持つ企業・団体・行政を見つけると、技術的なアドバイス、行政の手続き、資金調達の手法や工事事業者らのアレンジを含めて、事業計画の骨格を組み立てる。設計した事業を企業・団体・行政に手渡し、自らが事業運営を担うわけではない。コンサルティング料はとらず、受け取るのは工事手数料とメンテナンス料だけだ。

豊岡さんは自らが担っている業務内容はドイツのシュタットベルケに似ているという。シュタットベルケはエネルギーを中心にさまざまな地域公共サービスを担う民間主導の公益事業体であり、市民に技術サービスを自治体にはインフラを提供している。だが、事業を自ら作り出すという意味で、それよりはるかにアクティブ(主体的な活動)である。
豊岡さんは世界のエネルギー事業を見て回っており、世界的視野から日本はまるでガラパゴスのようだという。彼女の頭の中で描いている地域のイメージと現実との落差に歯がゆさを覚えてもいる。次々と事業を興し、広げていくには一人で背負うものを可能な限り減らし、多少なりとも「身軽」にならなければ、フットワークが失われてしまう恐れがあるという。また、豊岡さんには強い危機感がある。彼女は時々、エネルギー事業で海外視察に行くことがある。つい最近もスペインやスコットランドに行って電力システムを見てきた。日本は、エネルギー転換だけでなく先端産業分野でどんどん遅れていくというのが、いつわらざる実感だという。その意味で、後藤田知事の前例を打ち破る姿勢を、彼女は高く評価し期待している。このままでは日本は沈んでしまわないかと不安に襲われるが、せめて徳島だけでもノアの箱舟を作って生き残れないものかと真剣に自問することもあるという。

撮影:魚本勝之
かねこ・まさる 1952年、東京生まれ。東京大学経済学部卒業。法政大学経済学部教授、慶應義塾大学経済学部教授などを経て、現在、慶應義塾大学名誉教授。著書多数。近著に『平成経済――衰退の本質』(岩波新書)、『岸田自民で日本が瓦解する日』(徳間書店)、『高校生からわかる日本経済なぜ日本はどんどん貧しくなるの?』(かもがわ出版)、『裏金国家――日本を覆う「2015年体制」の呪縛』(朝日新書)、元農水官僚で農政アナリストの武本俊彦氏との共著『「食料・農業・農村基本法」見直しは「穴」だらけ!?』(筑波書房ブックレット)、『フェイクファシズム』(講談社)がある。




